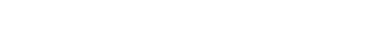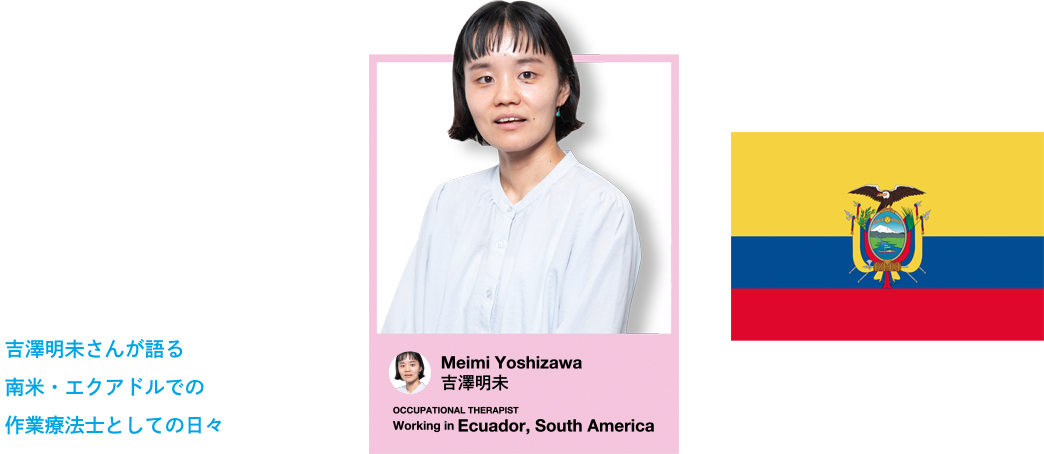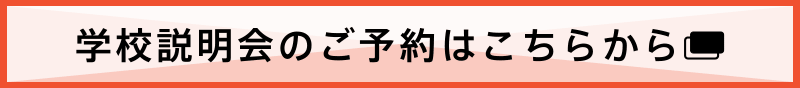鈴木友美
Suzuki Tomomi
高校卒業後、日リハ作業療法学科夜間部に入学。卒業後は精神科病院に数年勤務した後、青年海外協力隊でチュニジアで活動。帰国後から現在まで、訪問看護ステーションに勤務し、精神障がい、身体障がい、高齢者と幅広くリハビリテーションを行っている。




鈴木友美さんが語る
アフリカ・チュニジアでの
作業療法士としての日々
鈴木友美さんは、日本リハビリテーション専門学校 作業療法学科 夜間部を卒業後、精神科病院での勤務を経てJICA青年海外協力隊に参加されました。そして、2013年に発達障がい分野の作業療法士として、北アフリカのチュニジア共和国へ派遣され、2年間の支援活動を行いました。現在は訪問看護ステーションで精神障がいや身体障がい、高齢者への支援を行う鈴木さんに、チュニジアで過ごした日々や日リハでの学生生活を振り返っていただきました。


海外での活動を目指した理由
―鈴木さんが海外で活動を志したきっかけは、
どのような経緯があったのでしょうか?
それまで海外旅行でタイにしか行ったことがなかった私が、青年海外協力隊としてチュニジア共和国を訪問したのは2013年から2015年にかけての2年間のことでした。
日リハ時代の実習でデイケアに行く機会が多く、そこで経験を積み重ねるうちに、ゆくゆくは病院よりも地域で暮らしている対象者に向けた支援がしたいと思っていました。家で過ごす生活こそ、対象者の暮らしの個性が最も立ち上がってくるわけですので、そこに関わりたいと。実際、卒業後すぐに勤務した病院にもデイケアはあったのですが、所属先の事情でそちらへの異動はかなり先になってしまうことが就職後に判明しました。
将来的に地域で暮らす方への仕事に従事するならば、住む場所や家庭によって習慣や文化、価値観が異なるということをしっかりと念頭に置いておかないといけません。対象者を取り巻くそれらをあらかじめ察知し、最適な形で支援できるようになる力を身につけないといけないと思っていました。
そんな風に将来のビジョンについて考えるようになっていた時に、日本作業療法学会に参加したのですが、シンポジウムで青年海外協力隊に参加された方の発表があり、幸運なことにその発表者の方と飲みに行く機会を設けていただきました。そこから協力隊経験者などの勉強会に参加させていただくようになっていったのです。なによりも、文化が大きく異なる海外で暮らす方の支援について学ぶことができれば、いつか日本の地域で暮らす方のために働くようになった際にその経験が役に立つだろうと思い、協力隊に挑戦することを選びました。その時の私は臨床経験が3年程度でしたので、途上国で自分の能力を発揮するというよりも、自分自身が学びを深めることで糧にしていきたいという想いの比重が高かったですね。

いざ、チュニジア共和国へ。
海を渡る
―鈴木さんが派遣されたのは
どのような施設だったのでしょうか?
事前に協力隊経験者の先輩からは、日本との環境の違いはもちろん、作業療法士の絶対数の違いや人的資源や物的資源が異なること、宗教上の問題があること、リハビリテーションを優先するよりも彼らの信念に反する支援を行わないほうが良い場合があることなど、心構えを教えていただきました。結果的に私が派遣されることになったのは、北アフリカに位置し、地中海とサハラ砂漠に面したチュニジア共和国です。
派遣先は首都ではなく、車で2時間ほどの場所にある田舎の地域だったのですが、3歳から40歳くらいまでの知的障がい、ダウン症、自閉症、統合失調症の方が通う施設でした。日本における障がい児の通園施設や特別支援学校、障がい者の作業所がすべて一つになったような場所です。

当時のチュニジアは、2010年から11年にかけて起こった民主化運動の「ジャスミン革命」によって23年間続いた政権が崩壊した直後で、情勢がとても不安定でした。私はなんとか無事に2年間の任期を全うすることができたのですが、ちょうど私が帰国した日にフランスで「シャルリー・エブド襲撃事件」が発生したこともあり、この一件がもっと前に起こっていたら、任期途中での帰国を余儀なくされていたと思います。これは私が帰国した2か月後(2015年3月)の出来事ですが、チュニジアの首都チュニスにある国立バルドー博物館で観光客を襲撃したテロが発生し、日本人3人を含む外国人観光客20人以上が犠牲になりました。この時も派遣された人たちは全員が国外退避になったと聞いています。
当時の情勢不安は働く環境にも影響していて、実は働く施設も途中で変更になったくらいです。一つ目の施設の際は、運営が安定しておらず子供たちが来所できない状況になってしまったのです。二つ目の方が長く過ごしたのですが、そこでは一日50人くらいの方が来所されていました。
異文化の中で
作業療法士として活動
―これまで経験されたことがない異文化の中で支援を行うことはやはり大変でしたか?
それは大変なことでもありましたが、作業療法士としては興味深いと感じる部分もありました。例えば入浴動作の中で、お母さんが介助をすれば息子さんは入浴ができるというケースがあったのですが、イスラム教徒ばかりのチュニジアにおいては、男性と女性で生活空間を分けたほうが望ましいことが多く、そのため息子が一人で入浴できることに対して価値が高いとされていました。ですので、彼が自立できるようにリハビリを行ったり、母に家庭での指導法を伝えたりしました。他にもイスラム教はお祈りの前に手や足を洗ったり髪を濡らしたりという決まりの動作があるのですが、私はそれを意図せずにセルフケアとして手洗いなどを支援していました。ですが、その時に介助していたある男の子が「僕もこれを一人でできるようになりたいし、お祈りも一人でできるようになりたい」と言っていて、イスラム教徒として自尊心を高める作業でもあるのだと思いました。
特例として、障がいのある人は礼拝堂の前にある石に触ることで、礼拝前の動作が免除されるそうなのですが、その子の中には正式なプロセスを踏んでお祈りをしたいという思いが強く、イスラム教徒としての確固たる意志に触れたことが印象に残っています。これはまさに異文化を強く感じたことであり、日本とは異なる宗教的意味を持つ日常生活動作の支援について考えさせられました。

(写真)イスラム教の礼拝、身を清めて神に向き合う。
―日本で学ばれてきたことがどういう点で役に立ったと感じたことはありましたか?
作業療法は、対象者の能力などを知ると同時に、行っている作業や目指したい作業の分析も行い、リハビリで行う活動の展開へつなげます。あとは、環境の評価や自分の対象としている人を取り巻く集団がどういう状況にあるか見たり、集団の力を使って対象者の状況を改善させたりします。私の派遣当時、チュニジアはセラピストが少なく、「現地にいる作業療法士に技術移転をする」と事前に言われていたものの、実際に行ってみたら派遣先には作業療法士はおらず、自分だけでした。イスラムの戒律で女性が家にいることがすごく多かったりするので、一人しかいない作業療法士から一対一で対象者に何か支援をするよりも、その子のお母さんに伝えた方が本人の生活にとって有益なケースもありました。障がい者を助けることが宗教的に価値あることだったり、チュニジア人はもともと距離感も近い人たちでしたので、障がい児たちと街を歩いて、「こういう風に支援すればこの子たちはこんな風に買い物ができる」ということを実際にやってみたりして、直接地域の方が障がい者を助けられるよう周りの集団に対して働きかけることを実践していました。これはとても作業療法的な視点なのかなと思っています。一方で、発達障がいに関するイベントを行った際、たくさんのお母さんたちが情報を求めて参加しに来られたことがありました。前述の通り、イスラム圏では女性が外へ出ることを良しとしない夫も多い中で、子を想う母の強さや困っている気持ちを目の当たりにしました。

(写真)障がい者に対する情報提供イベントの風景。
異文化に対して
積極的にコミットする
―2年間を振り返って、鈴木さんにどのようなものをもたらしてくれましたか?
言葉の面でも、フランス語もアラビア語もチュニジアに行かなければ学んでいなかったと思うので、言語を通じて知り合う人が増えましたし、日本に帰国後もチュニジアやフランスにいる当時の同僚たちと連絡をとり、今回のコロナ禍でもそれぞれの国でどのように対応しているかなど情報交換していました。作業療法士的な視点でも、これまでは精神科の病院でずっと勤務してきましたが、たとえば日本の精神科病院で何か身体的な問題が起こった場合は身体科病院に転院してもらう手続きを取るのが通例ですが、チュニジアの派遣先では作業療法士が私しかいなかったということもあり、「自分のスキルを否が応でも高めるしかない」という事態に直面しました。それもあって、可能な限り何でも対応できるセラピストになっていこうという志向を抱くきっかけになったと言えます。

(写真)チュニジア人の一般的な食事です。ラマダンの時の夕食は1食目となり、胃腸が動いていない状態から食べるので必ず一番先にはスープを食べます。三角の揚げられたものはブリックと言い、中にツナやポテト、たまごなどを入れます。私が午前2時に口に入れられていたものです。
チュニジアで2年間を過ごすにあたって現地の生活になじむことを優先していました。服装はその最たるものですが、お金を持っていると思われて犯罪に巻き込まれたりしないようにするだけでなく、任地が首都から車で2時間の田舎町で貧しい方もいらっしゃったため障がい者や家族へ失礼にならないように、かつ親しみやすさを感じてもらえるように心がけました。
それ以外にも、宗教の違いによる異文化に対しても一線を引くのではなく、可能な限り自分でも理解できるように努力しました。たとえば、イスラム教の五行の一つ「断食」を一ヶ月に渡って行う「ラマダン」に私も挑戦してみたり。断食の苦しみや大切さを少しでも共有できればと思ったのですが、やはり過酷でしたね……。ムスリムの皆さんは日の出から日没にかけて一切の飲食を断つのですが、さすがに水を飲むことさえ我慢するのは難しいものがありました。JICAが探してくれた住居は、大家さんが1階に住み、私は2階で生活をしていたのですが、「冷蔵庫を開けた音や包丁で何かを切っている音が聞こえてきたぞ」と言われたことも。大家さんはとても敬虔なムスリムなのでそこまで言われたのですが、もちろん外国人に対して柔軟に対応してくださる方もいらっしゃいます。「料理を作るにしても窓を開けて匂いが漂うと失礼にあたるから、しっかり閉めた方がいいよ」とか「水を飲むとしてもみんなに見えないようにすればいいよ」と言ってくださる方もいらっしゃいました。

(写真)モスクのミナレットの写真。これが点灯し、アザーンが流れると食事をして良い合図となる。
―そこまで体験された方はほとんどいらっしゃないでしょうね……。日本で取り入れる人が多い断食とは全くの別物ですから。
ラマダンの時は、食べても良い時間になるとモスクに付随するミナレットという塔に電気が灯るのですが、その灯りを自宅の屋上で確認してからみんな一斉に食事を食べはじめます。逆に食べられなくなる時間が近づくと、真夜中の2時や3時でも無理やりたたき起こされて、「友美、もうすぐ食べられなくなるから!」と脂っこいものを食べさせられたりもしました(笑)。
チュニジアから帰国、
理想の作業療法士を目指して
―2015年1月にチュニジアから帰国され、そこで得たものを糧に、鈴木さんはどんな作業療法士になりたいと思われましたか?
これまで精神障がいを専門でやってきたので、その領域を続けていきたいと思っていた一方で、身体障がいの方を支援できるようになりたいという思いが強かったこともあり、そのどちらも看ることができる訪問看護ステーションに就職しました。チュニジアでの体験で“可能な限り何でも対応できるセラピストになりたい”という志向を抱いたとお話ししましたが、その想いが実現できる場所を選びました。同じ職場の理学療法士や作業療法士でも教えてくれる人はいたので、訪問に同行させてもらってその現場を見たり、私自身も勉強会に参加して学びを深めていったりなどを積み重ねています。
現在勤務している訪問看護ステーションは精神科だけなのですが、合併症で糖尿病や呼吸器疾患、整形外科疾患を併発された患者さんもいらっしゃいます。精神科の患者さんの中には、本来であればデイサービスやリハビリの場に通所した方がいいのに集団の場が苦手な関係でそれができない方や、年齢や疾患の種類で介護保険が適用にならず通所サービスが利用できない方がいらっしゃいます。それにかなり限られた条件をクリアしないと「訪問看護ステーションは2つ同時に入ることができない」という決まりがあるため、おのずと身体と精神どちらかしか入ることができない現状です。精神科の訪問看護ステーションでも、身体的なケアは必要になってくるので、身体科を診ているお医者さんに「こういうリハビリをしようと思います」とリスクの確認をしたうえで提供できるようにしています。また、精神症状や対象者の特性に合ったプログラムの組み立てをして心理的に負荷のかかりやすい方でも継続して実施できるようにしています。青年海外協力隊で行く国もそうですし、厚労省の制度上できないことがあったり、災害時の緊急事態もそうだと思いますが、様々な制約があっても、その中でどうすれば一番対象者にとって利益が出るような形になるかを考えて行動するようにしています。それはチュニジアでの経験が最も活きていることだと感じています。

日リハ後輩や作業療法士を
目指す人に向けたアドバイス
―今後、鈴木さんのように海外での活動を目指す作業療法士の方に向けたアドバイスとしてどのような言葉をかけられますか?
作業療法士に限って言えば、その人たちの生活を知ることが大事になってくるので、同じような生活を体験してみることは、必ず業務にも活きてくると思います。青年海外協力隊は、そもそも現地の人と同じ生活をすることが前提でもありますし、彼らと同じ生活リズムで生きることで理解できることも多々あります。現地の方が勧めてくれるものを食べたり、一緒に遊びにいったり、農作業をしたり、可能な限りやってみてください。そこを重視していたからこそ、私は“なぜその人たちがそうしているのか”について良く質問していました。
協力隊経由で行く場合、どこの国に派遣されるかによって異なるかもしれませんが、往々にして海外ではセラピストの数が少なかったり、物資がなかったり、保険制度や医療体制、資格の区分なども日本とは異なります。そのような環境では特に自分の作業療法士としての立ち位置というものを意識させられ、その都度“自分はどのように行動するべきなのか”を考える機会となります。もし、興味を持たれたら青年海外協力隊や国際リハビリテーション研究会のセラピストたちの活動をチェックしてみてください。
私も協力隊では、障がいを持つチュニジア人への支援を行うと同時に、自分自身が異文化の中でマイノリティとして長期間に渡って生活をしました。この経験を活かし、日本で暮らす外国人の障がい者や家族への支援も積極的に行い、彼らの生活がより良くなるように助力となっていきたいですし、作業療法が対象者や社会にとって役立つものであることを伝えられるような研究活動も続けていきたいです。
―鈴木さんにとって日リハで過ごした4年間はどんなものでしたか?
私は夜間部の所属だったため、仕事と学業の両立でとても忙しかったですね。昼間は学校に紹介していただいた高齢者のデイサービスと入所施設が一緒になったところでアルバイトをして、それが終わると学校で勉強という毎日でした。加えて、高校を卒業した直後の身だったこともあり、遊びたい気持ちもまだまだあったため、正直勉学に集中できていなかった時期もありましたし、追試もたくさん受けました(笑)。それでも作業療法士になりたいという想いを抱き続けていましたし、日リハで過ごす時間が経過するごとに、その想いはより強くなっていきました。
夜間部の特色としてクラスメイトが年上の方ばかりで、一番上の方で49歳。10代から40代までの世代が一つのクラスで学んでいました。夜間部では学費を自ら工面されている方も多く、勉強に対して真剣な姿勢にも大いに刺激を受けました。皆さん先生に求めているものも大きく、高校卒業直後でどうしても受け身にならざるを得なかった私とは対照的だったことを憶えています。
自身の未熟さゆえ、先生方にとっては手を焼いた学生だったかもしれません。2年生までは大西麓子先生が担任をしてくださり、3年生からは手塚雅之先生に受け持っていただきました。先生方は4年間を通して私に目をかけてくださり、時に叱咤し、鼓舞してくださったという思いが一番にあります。昼間部と比べて、どうしても夜間部の学生は学校にいる時間も短くなるのですが、そんな中でも先生が時間を作って話をしてくれたり、卒業時の課題の足りない部分の相談に乗ってくださったりしました。
また、実習期間中に同居していた祖父が急死し、そのショックから自分の実習への熱量が保てなくなりそうになってしまったことがありました。その際には、手塚先生とメールでのやりとりを通して叱咤激励をいただき、自分で最後までやり抜けるように支えていただきました。

―日リハで学んだからこそ身につけられたというようなことはありますか?
実習期間が長く、複数の分野や現場で学ばせてもらえたことは大きな経験となりました。私の実習先の一つに山形県酒田市があったのですが、冬に雪が降る中で行われました。その環境だからこそ必要な福祉用具があり、通所でなく入所しなければいけない事情が生まれたりした一方で、地域のつながりで車移動を対象者同士が支えあっていたり、雪深い中での農業を通した忍耐強さがリハビリへの姿勢に表れていたりと、地域性の違いを見られたことが興味深い経験となりました。
現在、私は地域で暮らす対象者への支援をしていますが、今後はさらに作業療法士が地域で働く機会が増えていくと思います。地域では精神障がい者も身体の合併症を抱えていたり、病院のように科ごとで分化されていなかったりするため、一人のセラピストが多領域で貢献できるほうが対象者の生活の利益となります。そのため、様々な実習を通じて、学生のうちから複数の領域に関して現場を通した知識を身につけられたり、指導してもらえる経験が積めたりするというのは間違いなく強みになっていきます。
―最後に作業療法士を目指す方へのメッセージをお願いします。
作業療法では、対象者の症状や病気の部分だけでなく、その人の好きなことや大事にしていることが何か、なぜそうしたいのかを理解するなど、相手を知ることも重要な仕事です。価値観の異なる方を理解しながら行う支援は難しくもありますが、その一方で相手の眼鏡を借りて違う世界を見せてもらうような感覚があり、それが醍醐味でもあります。
専門職として支援していくためには、在学中だけでなく卒業後もその土台になる部分を常に学び続けることが必要になります。日リハには学生のあらゆる疑問に対してしっかりと呼応してくれる個性的な先生がたくさんいて、学びを目の前の方に活かすことの楽しさも教えてもらえると思います。
私自身は4年間の学びに加え、チュニジアのような人的資源や物的資源に制限があるなかで働き、情勢的にも安定しない環境を経験し、異文化に積極的にコミットして生活したことで、イレギュラーな事態に対しても、問題解決能力がついたように思います。そして、その経験が今回のコロナ禍でも発揮されたように思います。例えば、コロナの影響でデイサービスなどの通所先が閉まってしまった方がたくさんいたのですが、訪問リハでの訪問回数や内容を変更して、デイサービスが担っていた役割をどのようにすれば補えるかなどを対応することができました。これから先、社会が様々に変容していくなかでも強みになるのかと感じ、そのような意味で若いセラピストにも青年海外協力隊などに挑戦してもらえたらと思っています。